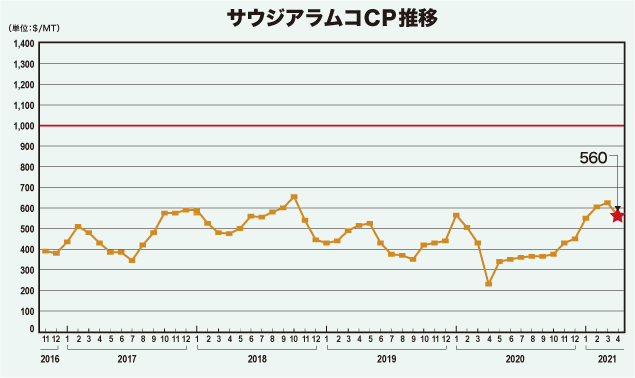なぜLPガス料金は原価安になっても下がらない?!

LPガス料金は原価安になっても下がらない傾向にあり、それには、一般消費者に知られていないLPガス業界特有の取引事情が大きく影響しています。適正価格のLPガス販売店と契約するためにも実情を把握することが重要です。

LPガス料金が下がらない理由を知る
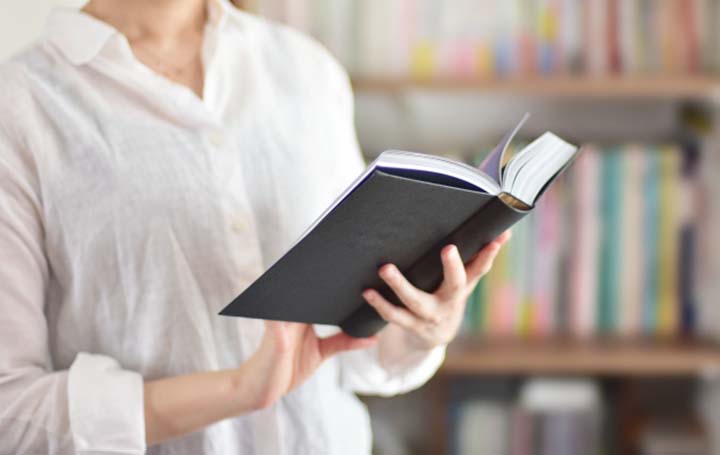
LPガスの原料費は、ガソリンと同じく為替レートや原油価格によって変動しているにもかかわらず、原油価格の上昇時にはLPガス料金を値上げしても、下降時では料金の値下げ幅は小さいか、全く下がらないことすらあります。
多くのLPガス販売店は、消費者のLPガス料金についての認識不足をいいことに、不透明な価格調整を繰り返しているのです。
こうした状況を踏まえ、経済産業省はLPガス料金の透明化に向けて、2017年2月に「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針」(取引適正化ガイドライン)を制定し、LPガス販売店に対して、消費者への適切な情報提供を行うよう周知徹底を求めています。
しかしそれも強制力がないので根本的な解決には至っていないのが実情です。
私たち消費者ができることは、ガス料金や仕組み、LPガス業界の実態についてもっと関心を持ち、適正な価格でLPガスを利用できるよう、自分自身で対策を講じることです。
<関連記事>:プロパンガス料金の適正価格 2025
LPガス料金をめぐる問題点
ここでは、「LPガス料金の取引慣行」、「輸入価格と連動しないLPガス料金」の観点で、ガス料金が下がらない原因をまとめてみました。LPガス業界の問題を理解することで、原価が安くなってもLPガス料金が下がらない理由が見えてきます。
LPガスは自由価格
電力や都市ガスは、従来から認可料金制であり、料金水準が行政により査定され決められてきました。小売全面自由化後も、競争が不十分な地域では経過措置として料金規制を残すことで、消費者の保護を図っています。
しかし、LPガス業界は昔から販売店が自由に価格を決められる自由料金制のため、電力や都市ガスと比較して、LPガス料金の妥当性や消費者保護が欠如しているのが現状です。
<関連記事>:プロパンガスは公共料金ではありません!
LPガス業界の談合構造
LPガス販売店は長期継続的な取引を守りたい考えから、お互いの顧客を取り合わないという商慣行により、一度獲得した顧客は固定化される傾向にあります。
このことからLPガス業界では価格競争が起こりにくく、料金の透明性を確保する動機がない談合構造になっています。
<関連記事>:プロパンガス業界最新状況と特有の悪習あるあるとは?
消費者間の料金格差
LPガス販売店が新規に勧誘する消費者には格安料金で供給したり、他の販売店から勧誘を受けた消費者を引き留めるために料金を下げたりすることがよくあります。
その一方で既存の消費者に対しては安い料金を適用せず、高止まりした供給料金を継続します。地域性や需要構造に差がないにもかかわらず、自由料金ゆえに消費者間に極端な料金格差が生じています。
料金情報の提供が不十分
「取引適正化ガイドライン」ではLPガス販売店に標準的な料金メニューの公表を求めていますが、なかなか進んでいません。公表できない大きな理由は、料金表が多数存在することです。大手業者では500種類以上といわれています。
どの料金表が標準的な料金か把握できないのです。これではウェブサイトに料金メニューが公表されていても、実際に自分が契約する時のガス料金がいくらなのかを正しく知ることは不可能です。消費者の「知る権利」が無視された状態です。
消費設備費用負担を巡る問題が法改正の根幹
プロパンガス会社が、アパートの大家さんに給湯器やエアコンなどを無償貸与するサービス攻勢をかけて自社の顧客として囲い込んでいる商習慣が、かつてはありました。
無償貸与のコストは入居者のガス料金に転嫁して回収する構図でした。事実を知らされていない、説明されていない入居者は自覚のないまま支払っている実態が浮き彫りとなり、2024年7月の法改正に繋がりました。
たとえば、給湯器などのガス器具のコスト償却期間は10年が一般的ですが、償却後も高額料金を継続する悪質なLPガス販売店もあります。顧客確保のための過剰投資で、消費者が理不尽な負担を強いられているケースも多いのが問題でした。
<関連記事>:アパートのガス料金が高い理由
LPガス料金の取引慣行は、販売店にとって消費者の目から料金内容を隠すことができるため非常に都合のいい仕組みになっています。これが「原価安になってもLPガス料金が下がらない」一因です。
外から見えない料金形態
LPガスは原油、CP価格に影響を受けているにもかかわらず、原油価格が下落しても、なぜLPガス料金は下がらないのでしょうか。
たとえば電力会社や都市ガス会社は、輸入した原油や天然ガスの価格をもとに料金を決定する原料費調整制度を採用しています。プロパンガス業界にはこの原料費調整制度がほとんど浸透していません。
料金の透明性向上のためには原料費調整制度の採用が適切ですが、料金値下げをしたくないというだけでなく、料金表の種類が多すぎて料金改定が困難、販売管理・料金システムの導入資金の不足などを理由に採用は全体の2割弱にとどまっています。
LPガス業界では都合よく消費者の目から料金内容を隠す料金形態が定着している状況です。
輸入価格が小売価格のわずか1割
輸入価格が小売価格に占める割合は1割程度に過ぎず、9割が流通段階で生じており、特に小売段階が6割を占めています。
小売段階では、LPガスボンベ配送のため配送費・人件費がかかります。また、保安面からも供給設備の点検や保安機器の設置などのコストが膨大にかかります。
その結果、流通コストの削減をしても配送・保安コストによって吸収されるため小売価格が下がらないというLPガス販売店側の言い分もあります。
しかし、原価について十分な管理、把握が行われていないこともあり、実際は料金表に示されていないため一概にはいえません。小売価格低減のためには、各流通段階、特に小売段階での合理化・効率化努力が求められます。
エネルギー自由化競争の中で、「上がれば上げる、下がれば下げる」という当たり前のことができないのがLPガス業界です。
原油、CP価格の変動をLPガス料金へ迅速に反映させることが求められます。
LPガス販売店は自分で選ぶ時代!
LPガス料金が原価安になっても下がらないのは、LPガス業界の都合のいい料金取引慣行が大きく影響しています。
この実態を受け、適正価格・安定供給に向けたガイドラインが制定されたとはいえ、どの販売店を利用しても消費者が安心できる状態とはいえません。
電気や都市ガスが小売全面自由化されている今、高いLPガス料金に黙って耐えている必要はありません。現在契約しているLPガス販売店が適正価格でなければ、LPガス販売店の変更をおすすめします。
LPガス料金が妥当かどうかの判断は、「いくら」なら適正かを知ることが重要なポイントです。しかし、販売店のウェブサイト情報だけでは正しく判断するのは難しいでしょう。
それが理由でガス会社の変更をためらっている方は、プロパンガス料金消費者協会にご相談ください。「適正価格・安定供給・安全確保」をクリアした優良なLPガス販売店を無料でご紹介します。
<関連記事>:ガス会社の変更でガス代30%削減!
- A.{{ item.num }}
なぜLPガス料金は原価安になっても下がらない?!まとめ
LPガス料金が下がらない理由を知るには?
消費者は、ガス料金や仕組み、LPガス業界の実態についてもっと関心を持ち、適正な価格でLPガスを利用できるよう自分自身で対策を講じるべきです。詳細はこちら。
LPガス料金の取引慣行とは?
「LPガスは自由価格」「LPガス業界の談合構造」「消費者間の料金格差」「料金情報の提供が不十分」などの問題が多く、LPガス料金透明化に向けて、ガイドライン、ルールを守る業界体質の改善が急務です。詳細はこちら。
LPガス料金はなぜ輸入価格と連動しない?
消費者の目から料金内容を隠す料金形態が定着している状況のほか、配送・保安コストによって吸収されるため小売価格が下がらないというLPガス販売店側の言い分もあります。詳細はこちら。
LPガス販売店は自分で選ぶ時代!
高いLPガス料金に黙って耐えている必要はありません。「プロパンガス料金消費者協会」にご相談ください。「適正価格・安定供給・安全確保」をクリアした優良なLPガス販売店を無料でご紹介します。詳細はこちら。

プロパンガス料金消費者協会
- ・1950年
- 群馬県伊勢崎市生まれ。
- ・1980年
- ソード株式会社(後の東芝パソコンシステム株式会社)に入社。
- ・2010年
- 一般社団法人 プロパンガス料金消費者協会を設立して理事に就任。
- ・2011年
- 同代表理事に就任。現在に至る。
- ・2023年
- BSテレビ東京「マネーのまなび」で、不透明なプロパンガスの料金について取材を受け、番組内で解説。
設立当時、プロパンガスは都市ガスに比べて約1.8倍も高い状況にも関わらず、消費者が相談できる団体は皆無であった。そこで、鈴木は消費者の立場に立って、不透明なガス代について料金面から取り組む団体として協会を設立した。
それまで存在しなかったプロパンガス料金の“適正価格”の設定に奔走。大手供給業者の賛同を得て、設立10年足らずで”適正価格“を共通言語として全国展開を達成し、130社以上のプロパンガス会社とパートナー契約している。
現在はプロパンガスの”適正価格“の指標になる「CP速報」を毎月執筆し、ガス料金の適正価格での供給に貢献している。